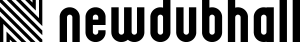ソロ作品
そして1994年にソロ1st『Nothing Much Better To Do』をリリースされます。
藤原1stはレア・グルーヴというか、生音中心でやってみたかったという感じでしたけどね。あの頃は、渋谷系というか、ある種のバブルだったので僕の1stですら、5~6万枚売れたんですよ。いまじゃ考えらないんですけど(笑)。そんな状況だったんでレコード会社もわりと好きなことをさせてくれていて、1stはゲストをフィーチャリングしたり本当にお金がかかっていて。当時、自分の心境としてはヒップホップから離れたかったんですね。だからサンプリングも使いたくないし、ラップも使いたくない。だから1stはああいうアルバムになったんですね。
でも、前後にそれこそ「N.I.C.E. GUY (NICE GUITAR DUB)」があったりとか、Hiroshi II Hiroshiがあったりと、メインではないですけど、ダブという表現がいつもあるという感じがあって。そして続くアルバム『Hiroshi Fujiwara In Dub Conference』は明確にダブというものをコンセプトにアルバムを作られました。
藤原1stを作った時点で、次はインストを作りたいというのがあったので、そのインストがダブだったということなんですよね。当時『羊たちの沈黙』という映画がすごい好きで、あの映画のなかのレクター博士が、グレン・グールドの「ゴルトベルク変奏曲」が好きという設定だったんですね。あの曲を朝本くんに、ピアノで弾いてもらって、あのピアノの旋律とダブっぽいものを混ぜるというのがそもそもの始まりですね(「Natural Born Dub」)。
そういう意味ではサンプリング的な発想とダブとのミックスですよね。
藤原そう、1stは全部生音だったけど、このときはそういう感覚があると思う。
この時期、朝本さんとリミックスやプロデュースも含めてわりと組んでやられてましたよね。
藤原そうですね、たくさんやりましたね。僕と朝本くんと、そこに宮崎くんがいるっていうね。豪太とかK.U.D.O.がロンドンにいたときに、プログラミングとかをできたのが宮崎くんだったので、最初に一緒にやりはじめて。それからミュート・ビートのつながりから朝本くんを紹介されていう感じで共同作業がスタートしました。この3人のコンビネーションがチームのような形になっていくんです。エンジニアリングとかプログラミングで、宮崎くんがいて。僕がアイディア・ソースを持ってきて、それで朝本くんがちゃんとした演奏ができて、音楽的な理論もわかっていてという。この3人がとても良い関係性だったんですよ。僕はいまだに楽譜も読めないですけど、持ってきたアイディアを元に、朝本くんがアレンジを全てやってくれてという。
朝本さんとのお仕事で印象的だったことってなんですか?
藤原朝本くんは…… わりと音楽的な部分で闘ってくれたりしましたね。自分のようなDJ出身のプロデューサーの音楽って、音が外れているところとか、ベースラインが当たっているとか、そういうのを気にしないでおもしろいアイディアのものを作るという部分が良かったりするじゃないですか。でも、その価値観とは全然関係のないポップ・ソングのプロデュースとかしていると、もともとの音楽をやっている人たちにとってみたら、僕らの作るものが音楽理論的にやっぱり変なので、「この音どう考えてもおかしいでしょ」とか言ってくることがあるんですよ。でも、自分はそれを音楽的な言葉で返せなかったんですけど、朝本くんはちゃんと音楽理論の言葉で返すことができるという。そこの部分で防波堤になってくれた部分はありましたね。僕らはそういう理論みたいなものを無視して、サンプリングのチューニングがずれてても、サウンドのおもしろさを優先して使っちゃうようなタイプだったんですけど。朝本くんはそれをおもしろいと理解していて。当時の音楽業界の人たちからしたら「そんなチューニングのずれている音、耳がダメ!」という感じで。そういう人もいましたね。そういう意味ではおもしろい時代でしたけどね。

フィールドをつなぐ
1990年代の同時時代のアブストラクト・ブレイクビーツとかはどうでしたか? それこそ〈メジャー・フォース〉が大きな影響を与えた〈モワックス〉とか。
藤原当時はレア・グルーヴ的なものが好きだったりしたから、特に聴いてないかな。〈モワックス〉とかはぜんぜんかな。ただし、この人すごいなと遠目で尊敬してた人はDJクラッシュ。もともとヒップホップから出てきて、全然違う方向にいって、ひとりで孤高に闘っているという感じがあって。僕はそんなに交流ないんですが、DJクラッシュはかっこいいなと思ってましたね。
当時、UAさんとか、いわゆるポップ・フィールドとアンダーグラウンドなクラブ・ミュージックをつなぐようなサウンドをプロデュースでもされていたじゃないですか。
藤原僕は基本的に歌謡曲的なメロウなものも好きで、プロデュースなんかの仕事のときはそっちに寄せすぎる感があって。だから自分のなかでは日本のポップ・ミュージックとそういった洋楽的なヒップホップとかを混ぜることに関して成功できなかったというコンプレックスを持っているんですよ。
ええ、そうなんですか。
藤原そこはテイ(トウワ)くんとか本当にすごいなと思ってて。クラブ・ミュージックっぽいワン・コードで押しながら、ポップな曲を作ったり。僕はついつい歌謡曲っぽいコード進行感を出してしまうんですよ。ラヴァーズ感というか、そういう風になっちゃうんですよね。だからテイくんのやっていた感じはうらやましかったですね。
でも、自分のような世代は、そういったポップなものを通して、ダブとかラヴァーズ・ロック・レゲエを見つけたりということが起きてたと思うんですよね。当時は雑誌とかでチャートやセレクト的なものがいっぱいありましたね。
藤原僕らももちろん同じようなことを海外の音源から学んでやっていたということなんですよね。いまはそういうルートが途絶えちゃった感じはありますが。

ダブということでいうと一番好きなアルバムってなんですか?
藤原やっぱりデニス・ボーヴェルものかな。UKラヴァーズ~ダブという感じのところが一番好きかもしれませんね。もちろん、キング・タビーも好きですけどね。タビーはやっぱり、エンジニア気質なんでどんな曲でもああいう風にしちゃうけど。あとは過激なダブということになると、ニューウェイヴ的なニュー・エイジ・ステッパーズとかカラーボックスとかそういうものになるかな。
最新作『slumbers』でもメインではないですけど、やはりその音の質感はダブの空間処理ですよね。
藤原もう、これは自分の音楽を作る上で一生あると思いますね。そういう人、多いと思いますね。でも、例えばブラッド・オレンジとかも、そういうダブ感ありますよね。前のアルバムなんかは、もろにそういうUKのサウンドをサンプリングしてたりね。自分もサカナクションのリミックスを2年前にやったんですけど、それもダブっぽかったっすね。もうね、染み付いてますね。あと最近の削ぎ落とした、ネイキッド・リミックスみたいなものにもある意味ダブを感じますよね。
少し話が戻ってしまいますけど、『HIROSHI FUJIWARA in DUB CONFERENCE』でバスキアを使われたのはなぜなんですか? ダブ・アルバムでバスキアという。
藤原あれは日本で出ている作品の裏表紙に使われている絵なんですけど、それがずっと好きで、ピアノのダブのアルバムだったんで、使いたいと。バスキアというよりもピアノを象徴するようなイメージとしてつかったという感じですね。
ピアノ・ダブのアルバムというコンセプトのなかで決まったと。
藤原そうですね。
バンドみたいなものでダブをやるというのは考えたことなかったですか?
藤原バンドっていうのは考えたことなかったですね。やっぱりエンジニアの音楽ですからね。マッド・プロフェッサーのライヴとかもおもしろかったですけどね、〈イエロー〉でみたのかな、自分で作ったリミックスのマスター音源持ち歩いで、それをライヴ・ダブ・ミックスをするという。シャーデーのアカペラかけながら、ライヴでやってたり。
藤原さんもリミックスということでいえば結構な数ありますよね。
藤原出なかったやつもあるんですよね。安室奈美恵さんのリミックスもお蔵入りになっているのがあるんですよね。ラヴァーズのヴァージョンですね。
うわ聴いてみたいですね。
藤原X-JAPANもやっているんですよね。X-JAPANはLAのYOSHIKIくんのスタジオに呼ばれて、リミックスをやるということになって。そのリミックスの作業を見たかったんじゃないかと思うんですけど。YOSHIKIくんってすごい研究熱心で作業を見ていて、すごいまっすぐでいい人なんですよ。だからそのスタジオで「ここの部分、ピアノの素材が欲しい」っていうと、すぐにその場で弾いてくれるんですよ。
すごい話ですね。貴重なお話をありがとうございました。

location:Prefab black door
interview date:2018.09.06