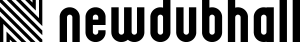表現の自由
さきほども少し話がでましたが『Requiem DUB』からは、ヤマハのQYシリーズという、VHSのテープを一回り大きくしたぐらいの音源とシーケンスが一体型になった機材を使って、トラックはおひとりで作られてたんですよね。
こだまそうです。
ベースなんかもQYで?
こだまそうです。
そうとは思えない音なんですよね。例えばロイド・バーンズがミックスで参加した『Requiem DUB』とかはどう録ったんですか。
こだまあの機材をCDというか、ちゃんと音源化するのは大変なんですよ。MIDIデータをどこかで再生するというわけではなくて、QY内部の音、そのものを使っているから。だから内部でミックスして、機材から出て来る音は2ミックスでしかないんですよ。
ですよね。
こだまそれを各チャンネル、各パートをそれぞれバラして、つまりレコーディングする楽器以外はミュートしてソロとして再生して、「ハットいきます」って、それをマルチにそれぞれ落とすんですよ。そのマルチ・トラックの素材を再度エンジニアがミックスするという。
なるほど、それは結構な手間ですね……。
こだまそうなんだよ、デジタルなんだけど、そこまでデジタルではなかったんだよ。もうみんなパソコン、ラップトップでいろいろやってたんだけど、僕はそこに立ち遅れているわけだからさ。それでもひとりでできるという、QYを手にしてしまったんだよ。それを教えてくれたのが譲だよ。
え、柏原譲さん(フィッシュマンズのベーシスト)。
こだまデジタルに疎い僕をみるにみかねて、譲が曲作りのメモがわりに使ってて。「これ、ちょっとメモ用に簡単でいいんですよ」とか、しゃらくさい感じでさ。
いやいや(笑)。
こだままさかそれを本番の録音に持ち込もうなんて感じではなくて、本当にメモ用にという感じで譲が教えてくれたんだよ。そっからだよね。はじめたのは。
そこではじめてほぼ人を介さずにこだまさんが電子音で音楽を描くということがはじまったんですね。
こだまそうそう。
なるほど、そうしたスタイルを築き上げる途中にリズム&サウンドに出会うと。それまでの試行錯誤も含めて、最終的には、ある種、ベルリンの彼らと同時代的な『Requiem DUB』が生まれると。
こだまそうなんだよ。そのもっと前を辿れば、あの静寂な感じはもちろんブライアン・イーノもあるよ。あのアンビエントからのインパクトはあると思うけどね。でも、その後、強烈に1980年代はレゲエに入っていく。そうして、時代のなかでミックスされていく、混沌としたセンスみたいなものが自分のなかで発酵していくんだよね。バンドを離れてひとりになったときに、そういうものを全部吐き出そうとするというか。シーケンサーが自分で操れるとなんでもやれるわけだから。「今日はいきなりパンクなリズムをやってみよう」とか思い立ったときにできるわけだから、それはいきなり表現が広がるよね。つまり、いつでも絵が描けるという。みんなで集まれたときに一緒に絵を描いていたのに、ひとりで思いついたときに絵を描けるっていうね。これは際限がなくなるよね。
まさに表現の自由を手にいれるという。
こだまそれが僕にとってのQYだったんですよ。
KTUのトラックもこだまさんなんですよね。
こだまリトルテンポの土生と二人で。

Undefinedとの共鳴
ビクターからのソロ・アルバム軍はまさに、こうして作られた音だったと。で、そこからいきなりいまの話で恐縮なんですが、「New Culture Days」を作ったときはどうだったんでしょうか。この作品を聴いたとき、僕はすぐ『Requiem DUB』やKTUといった作品をすぐに思い浮かべたんですが。
こだまいままで話してきたような僕の音楽を話さずとも共有しているアーティストなんじゃないかと思ったよ。それはあの曲を聴けばすぐにわかりますよ。ただ、何度も言いますけど「リズムがない」「ビートが途切れている」というのは、それはいままでになかったことだから。でも僕はそこを魅力と捉えたんです。些細なことだけど、音楽的にラジカルなことになるということはやっぱりあるんですよ。僕のQYのサウンドもある意味でそうだと思う。みんながもうパソコンを使って、もっとすごいクオリティのサウンドは作れる、そんな時代に立ち遅れていって、QYで楽曲を作る。でも「それのどこが悪いんだ」というね。ジャマイカの「スレンテン」、ダンスホール・リディムのはじまりには見事にカシオトーンがあるわけじゃない? そんな感覚というのは自分にはあって。人にばかにされてもいいから、自分がいいと思えば「自分の絵の具として絵を描くよ、俺は」というね。この曲のデモを聞いたときに、これはなかったこと、キープされるべきビートが途切れてもなにか表現したいことがあるんだなって、すごいラジカルなものとして感じとったんだよね。
本当、レゲエがそこにいた残り香だけがあるような不思議な感じですよね。脳が聴こえない音を補完するみたいな感覚もありつつ、ちゃんとレゲエのリズムの残り香はあってという。
サハラ僕らの場合、ふたりの間では、メトロノームがイヤフォンではなっていて、それを聴きながら演奏するんです。だから、その分、みなさんには聴こえない、繋がっているリズムがあって。そこで感じ取れる部分があるんじゃないかなと思ってます。結成当初Undefinedは、ずっとベーシストを探していて、でも自分たちが作りたい世界観に合致するベーシストがいなくて。そこはある意味でさっきこだまさんのQYの話と通じるところがあるのかもしれないですけど、ベーシストがいないことでできた表現というか。ふたりだけでレゲエをやるというので、楽になれて自由にできたのかなっていうのはいま思うとありますね。
そういう意味でも本当、共鳴っていうのがあったんですね。
こだまうん、聴いたときにすぐにそこを良い部分として僕は捉えたんですね。これほどまでに音を省くというのを、良い意味で挑戦的と捉えたんですよね。世の中はリズムに溢れているわけだから、どんどんポップじゃなくなるわけですから。かといって、アヴァンギャルドじゃないのがいいところなんですよね。

新たな風
THE DUB STATION BANDがあって、あと最近では例えば客演でいえばSILENT POETSがあって、それぞれ感覚が違いますよね。
こだま根本的にバンド・サウンドは違いますからね。ここ最近の活動はライヴ中心になってきているわけです。2017年にNewdubhallから依頼があったんだけど、その後に不思議なもんで、下田(Silent Poets)くんからの依頼が来るんだよね。現状やっているのは、相変わらずバンドでスカとかロックステディあり、ルーツもありの、どが付くようなレゲエをやってるわけですよ。このインタヴューでNewdubhallにちなんで話していることとは全然違うね。あと録音の依頼ってほとんどなかったんですよね。それこそBEAMSの40周年の動画(『TOKYO CULTURE STORY 今夜はブギー・バック(smooth rap)』)ぐらいですよ。そこで8小節だけ吹いたぐらい。だからNewdubhallのレコーディングをきっかけに動いたんだよね。それも巡り合わせだよね、不思議なもんですよ。
『ひまわり HIMAWARI-DUB』のCDが出たばっかりなのでちょっとそちらのお話も。12インチやCD、さらには活発にバンドとして、ここ数年活動されていると思うんですけど、きかっけはあるんですか?
こだまやっぱり、ベースの河内が僕の背中をものすごい押してくれたことだよね。最初期のTHE DUB STATION BANDが中断して、ドラムが抜けて…… 間の時期が空いている時期にベースの河内がどうしてもやりたいという話をしてきてくれて。そっから話したことだよね。彼がいなければ、いまの活動はないよね。
クアトロのライヴもすばらしかったです。
こだまありがとう。
音の結束感もすごくて……。凄みというか。
こだまやっぱりそれはリハーサルで音を出すときにすぐに感じますよね。リズム隊から出て来る音圧、それはすごく感じてますよ。
しかし、それがさらに広がる形で世にでるというのはすごく良いことかなと思います。
こだまレコーディングをしたいというのはみんな感じていることなんですけど、いまは不遇な時代だからね。キーボードのHAKASE-SUNは10枚を超えるソロ作品を作っているけど、それだって自分でプライベートななかで録音して作ってるわけだからね。それをバンド・サウンドでレコーディングというのは違う、やはりそれはとても不遇な時代なんですよ。ましてやみんなすごいメンバーでね。それでも作品を発表することの困難な時代という。12インチでまずは聴いて欲しくて、それがやっとのことでCDで聴いていただけるようになったというだけですよ。
前作の『MORE』から10年ぐらい経っているんですよね。
こだまTHE DUB STATION BANDはやれているけれども。その間も、たとえば自分のソロはやれてないわけですから、いかに厳しいかという。そういうところに風が吹いたのは、Newdubhallから依頼がきたところ。「このサウンドで音源を作ろうとしているのか」という、そのよろこびもありました。もしコンスタントに『Requiem DUB』みたいなソロの作品ができていればいいんだけど、それもできずに10年以上の時間が経って、それを抱えているわけですよ。もちろん自分が悪いと言えばそれまでなんだけど、ソロの作品を出せないというストレスとともに10年以上の月日が経つ。でもそのときにNewdubhallみたいなサウンドの依頼がきたのはうれしくてね。偉そうな言い方をすると一番いいときに僕のことを突っついたなっていう感じがするんだよ(笑)。やりたくてもやれなかったなにかをやれるというのを持ち込んでくれたというかさ。そこに重なってSILENT POETSの下田くんの依頼もあって、それはほとばしるものもあるよね。

location:フクスケ/FUKUSUKE at 国立
interview date:2018.03.28